よく、「安楽死と尊厳死はどう違うのか?」ということを聞かれる。なかなか簡単には答えられない。どう違うも何も、「違う」と言う人にとっては違うし、「違わない」と言う人にとっては違わない、とも言えるからだ
安藤泰至(2019),安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと
1. はじめに:このページの役割
尊厳ある生と死をめぐる対話には、専門的な言葉や様々な意味合いを持つ言葉が登場します。このページではそれらの言葉の基本的な意味を解説すると共に、このサイトではどのような文脈でその言葉を使っているのかを、私たちの考えと共に示します。
ここで得た知識があなたの思索をより深く確かなものにするための一助となれば幸いです。
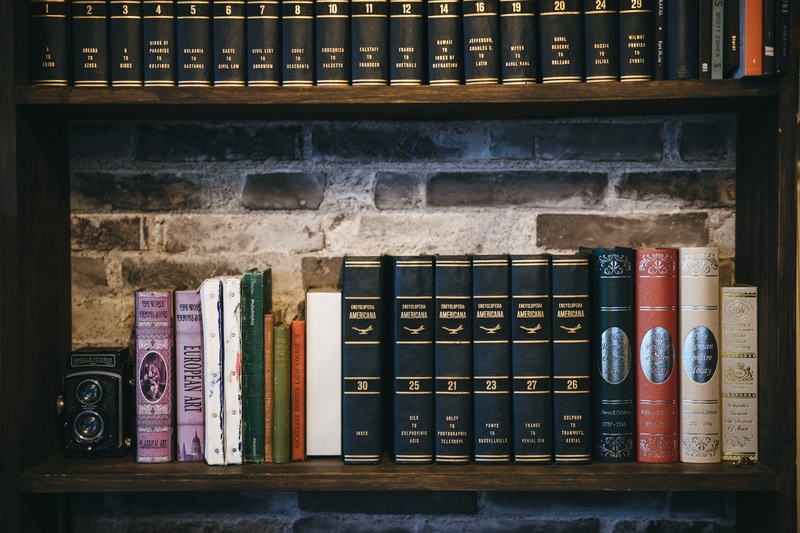
2. 用語と解説
【尊厳死】
- 基本的な意味: 回復の見込みがない末期状態の患者に対し、本人の意思に基づいて生命維持治療を差し控えたり中止したりして、人間としての尊厳を保ちながら迎える自然な死のこと。「本人の意思」と「延命治療を差し控えるまたは中止」という点で安楽死とは区別されます。日本の法律では認められていませんが、厚生労働省のガイドラインなどに基づき、患者本人、家族、医療チームの慎重な話し合いを経て延命治療が中止が行われています。
- 『思索の森』での文脈:当ブログでも「延命治療の手控えと中止」として扱います。加えて、単なる医療的な選択肢としてだけでなく、「尊厳ある最期とは何か」を考えるための、より広く哲学的な単語として捉えています。文脈の中では医療行為とは無関係な「尊厳がある死・尊厳が守られた死」として語ることもあります。死のあり方を選ぶことを通じて、「どう生きるか」を問い直すためのキーワードです。
【安楽死】
- 基本的な意味:本人の希望に基づき、人の苦痛を緩和するために、医師などが薬物を用いて患者の死期を積極的に早める医療行為のこと。「積極的安楽死」とも呼ばれます。患者本人が望んでいたとしても、他者が意図的に死をもたらす行為は日本の法律では認められていません。
- 『思索の森』での文脈:単純な安楽死とした場合、当ブログでは「積極的安楽死」を指す言葉として語ります。「尊厳死」との違いを明確にし、その意味を知るための重要なキーワードです。しかし、当ブログは、個人の心、社会、文化、習慣という多方面の話題を扱います。文脈によっては単純に「安らかな苦痛のない死」を意味して使う場合もあります
【広義の安楽死】
- 基本的な意味:積極的安楽死、医師幇助自殺、尊厳死(延命治療の手控えと中止)まで含みます。
- 『思索の森』での文脈:本ブログでも上の3点を含み扱います。加えて、時代や地域により解釈が変わる点にも注目します。私たちにとっての「安楽な死」を考える上での重要な考えです。ニュースや議論で『安楽死』という言葉が使われた際に、発言者がどの範囲を意図しているのかを冷静に読み解く助けにもなります。
【積極的安楽死】
- 基本的な意味:患者本人の自発的な希望に基づき、医師が致死薬などを「直接投与」することで、患者の生命を積極的に絶つ医療行為のこと。「嘱託殺人罪」や「同意殺人罪」に該当すると考えら日本の法律では認められていません。オランダやベルギーなどで認められています。
- 『思索の森』での文脈: 当ブログでは一般的にイメージされる「安楽死」(積極的安楽死)として扱います。「尊厳死」「医師幇助自殺」との対比で用いられることが多い言葉として扱います。医師が最後の行為の主体となる点で「医師幇助自殺」とも異なります。この行為が認められる社会の倫理観や、それがもたらす影響について多角的に思索するための重要なキーワードです。
【医師幇助自殺(PAS)】
- 基本的な意味: 医師が患者の自殺を「幇助=手助け」する行為のこと。例として、医師が致死薬を処方し患者自身の手によってその薬が服用(または投与)されることで死を迎えます。最終的な行為の主体は、あくまで患者本人です。Physician-Assisted SuicideからPASと呼ばれます。日本の法律では認められておらず、殺関与罪に問われる可能性があります。
- 『思索の森』での文脈: スイスやアメリカの一部の州で採用されているこの方法は、「自己決定権」を最大限に尊重する形として注目されます。当ブログでは、現実的な手段として、そして「自分の手で人生を終える」という選択の意味を、個人・社会・文化から【知る】と【考える】のカテゴリーを横断しながら考えていきます。
【持続的で深い鎮静】
- 基本的な意味: 回復の見込みがない終末期の患者に対し、治療が困難な耐えがたい苦痛を和らげる目的で鎮静薬を持続的に投与し意識レベルを深く低下させ苦痛から解放する医療行為のこと。以前は「間接的安楽死」と呼ばれることもありましたが、現代の緩和ケアではその目的が「苦痛の緩和」にあるという点で安楽死とは明確に区別されています。「終末期鎮静」や「セデーション」とも呼ばれます。もっとも広い意味の安楽死に含まれることもあります。
- 『思索の森』での文脈: 当ブログでも「死を早めること(安楽死)」と明確に区別します。あくまで「苦痛の緩和」を目的とし、病状が進行した結果として訪れる自然な死を穏やかに迎えるための一つの選択肢として捉えます。安らぎを得るという選択は「安楽な死」という問いに対する一つのあり方として探るべきテーマだと考えます。
【リビング・ウィル(Living Will)】
- 基本的な意味:個人が生きているうちに(living)、将来意思表示ができなくなった場合に備えて医療に関する希望を書き記しておく意志(will)。自分の意思を伝えられなくなった時に備えてどのような医療を望まない(あるいは望む)を、元気なうちに文書で示しておく「生前の意思表示書」のことです。主に延命治療の希望の有無など医療行為に関する具体的な希望を指します。事前指示書とも呼ばれます。
- 『思索の森』での文脈:医療や法的な側面だけでなく、自分自身の価値観と向き合い大切な人と対話するプロセスそのものを重視します。【考える】カテゴリーにおける「人生会議」内の具体的な一つと位置づけています。
【人生会議(ACP)】
- 基本的な意味: もしもの時に備えて自分が望む医療やケアについて前もって家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合うプロセスのことです。「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」とも呼ばれます。繰り返し話し合うプロセスそのものが重要であると強調されています。
- 『思索の森』での文脈:本ブログでも対話を続ける「継続的なプロセス」であることを大切にします。これは、私たちのブログが目指す「尊厳ある生と死をめぐる対話」そのものであり、議論の場をWEBへ拡大したものが本ブログです。
むしろ、「安楽死」や「尊厳死」について私たちが語ろうとするときに、第一に知っておかなければいけないのは、「安楽死」や「尊厳死」というものについて、何か世界共通の定義とか、 学問的に公認されている定義というものは存在しない、という事実である。
安藤泰至(2019),安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと
言葉や生き物です。文脈やその発言のあった時代により言葉の意味は変わります。
「安楽死を望みます」この一言に含まれる言葉の意味をこのブログを通じてともに考え行きたいと思います。

コメントを残す