こんにちは。『思索の森』へようこそ。今回は、Xで話題の「国は安楽死を認めてください」というネットデモについて、特別編として対談形式でお届けします。案内人の水野さんと、私、森田がゆるくこのテーマを語ります。
「国は安楽死を認めてください」とは
「国は安楽死を認めてください」というハッシュタグを使ったネットデモ活動は主にX(旧Twitter)上で展開されているオンライン運動で安楽死の合法化を求めるものです。この活動は参加者がハッシュタグを付けてポストを投稿し、社会的な議論を喚起し政府や世論に訴えかける形で行われています。
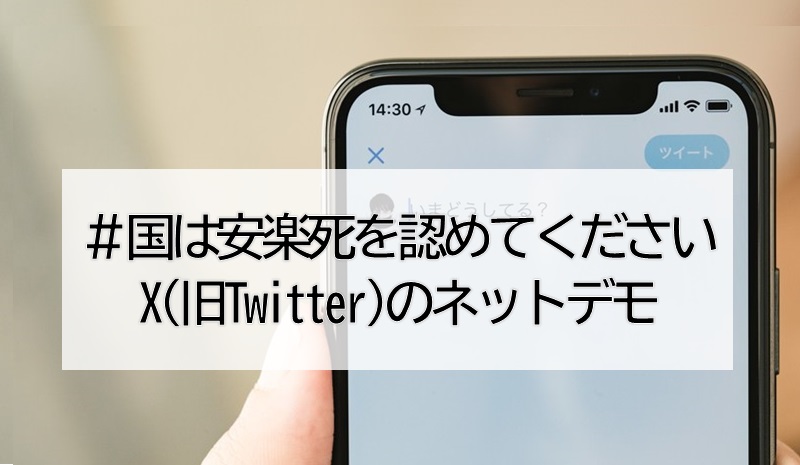
このデモで社会が変わるのでしょうか。今回の対談では、個人のつぶやきから、強さを求める社会への変化、つぶやきお祈り説まで話題が出ています。
水野
森田さん、Xで「国は安楽死を認めてください」というネットデモが盛り上がっていますね。ハッシュタグがトレンド入りして、さまざまな意見が飛び交っています。調べてみると2023年ごろから始まった活動のようで、その活動も大きくなっている気がします。普通、ネットのデモっていうと数日から数週間で終わってしまうイメージなのにこの活動は違いますね。森田さんどう思います?
森田
そうですね、息の長さすごいですよね。通常のネットデモとは明らかに違います。これ、何が原因だと思います?
水野
ハッシュタグを見ると、個人個人の叫び声みたいなものが集まっててる感じがします。「みんなも辛いんだな」って。安楽死って単なる政策の話じゃなくて、個人の思いと恐怖が絡むテーマじゃないですか。だからこそ、こんなに多くの人が声を上げてるんだと思います。
森田
確かに切実さありますよね。それと今「個人個人の声」って言いましたが、私もその感覚があります。このデモが長く続いているっていう事と関係あると思います。このデモは「社会活動」というより、本質的には「個人のつぶやき」の集合じゃないかな?個人の声が重なって活動のように見えている。だから普通のデモとは性質が違うんだと思います。これ、Twitterが本質的に「独り言」をつぶやく場所だから成り立つことだと思います。
この活動で私が考えたことがあって、昔のTwitterって「死にたい」「つらい」ってつぶやく場所だった気がします。でも今は時代が変わった。今は「つらい」とか「死にたい」なんてつぶやけなくなったように感じませんか?その結果、「つらい」って「心のつぶやき」が、「尊厳死をみとめたください」って「要求」に変わったんじゃないか?ってことです。実際は「死にたい」とセットで用いられていることが多いのですが…全体の空気が。
水野
以前よりは「死にたい」はタブーになった気がします。もちろん今もそういったつぶやきは沢山ありますけど、やっぱり社会として「つらい」とは言いづらくなった。そういえば、先日話した本(安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと)に出てきましたよね。「強い自分でいなきゃ」ってプレッシャーの話。実際、「つらい」ってつぶやくより、「尊厳死を要求する」方が意志もあって強く感じる。無関係じゃない気がします。
でも、これ、私たちにとっていい話ですか?自分の心を素直につぶやけなくなった、って事だとしたら、逆につらいです。
森田
素直な心がつぶやけなくなったら、確かに苦しいですね。捌け口もない。心の共有ができない。そうすると、「心が共有できない社会」だから「制度に救いを求める」ようになった、と考えることもできます。だとしたら、このデモの本質は「誰かとの繋がり」とか「一体感」が根底にあるのかもしれませんね。
水野
じゃあ、結局はこのデモは個人のつぶやきで、社会を変えることはできない?
森田
あの、少し話が脱線するんですが、私はこの話題を考えたときから、「つぶやき」が「お祈り」に似ているなと感じたんです。神様にお祈りする、あの「お祈り」です。要は、以前に話した「ぽっくり信仰」の様なものです。あの「お祈り」の現代版が、この「つぶやき」じゃないかって感じるんです。神さまに祈るの習慣がなくなった現代、ネットに書き込むことで何かしらの救いを求めるんじゃないかと。どこかに届くといいな、って。言葉と形は変わっても「救いを求める気持ち」は変わらないんだと実感しています。だから、ある意味では、このデモに参加して、一体感を感じて、神様に祈るようにその言葉を届ける、それで目的は達成しているのだと思います。水野さんはどう思いますか?
水野
その視点は面白い。でも私は、この運動は現実の社会を変える力があると思います。先日の参院選でも、個人でも集まれば政治を変える力があるとわかりましたし、何より「実際に尊厳死を求める声が上がっている」、この事実は変えられません。社会はこの現実を直視しないといけません。正直、私には祈りより「叫びと焦り」に聞こえる。それに、現代のITを使えば個人の声も可視化できそうですよね。AIを使って解析したり、意見をまとめたり。つぶやきお祈り説風にいうなら、AIが神様の代わりにつぶやきを聞いてくれる時代が来るかもしれません
森田
そうなると個人の声の重要性は増しますね。声が形になる可能性が出てきてます。これからもこの活動には注目していきましょう。

今回の対話は、ここで一旦終わりとなります。私、個人的には「国は安楽死を認めてください」という活動はとても重要なものだと考えています。 実際に社会を変える力を持っていると感じています。なぜこのような声が上がり続けるのか、今回話せなかった内容を含め、今後もこの活動は定期的に追っていきたいと思います。 このブログでまたあなたと共に考えられる日を楽しみにしています。
最後に、この記事を読んでくださったあなたはこの活動についてどう思いますか?賛否問わず、素直な意見をお待ちしております。
関連投稿
安らかに逝きたい。現代の「ぽっくり信仰」
【書評対談】『安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと』を読む
pol.is(ポリス)

コメントを残す